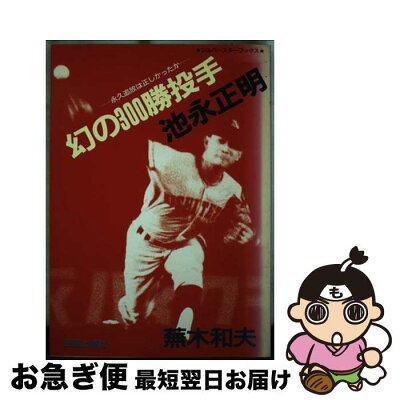1970年、球界を激震させた『黒い霧事件』で主力4選手が永久追放になった西鉄ライオンズ。
しかし思い返せば『鉄腕』稲尾和久氏監督就任1年目が、この『黒い霧事件』の年だったのは、稲尾和久氏にはご不幸としか言いようがないですね。
1 三 船田和英
2 二 基満男
3 中 ポインター
4 右 東田正義
5 一 広野功
6 左 ボレス
7 捕 村上公康
8 遊 甲斐和雄
9 投 池永正明
1970年の西鉄ライオンズの開幕オーダーはこんな感じで、古のプロ野球ファンには馴染み深い名前も見れるなかなかのものです。
4番の東田正義氏は後に阪神タイガース、2番の基満男氏は大洋ホエールズのセリーグでも活躍されたので、当時のパリーグの選手にしては比較的有名だと思います。
また1番の通称「ライフルマン」(同名テレビドラマ主演のチャック・コナーズに似ていたから)、船田和英氏は読売ジャイアンツからトレードでやってきた選手でしたので、かなりの有名選手でした。
が、船田和英氏は『黒い霧事件』で11月まで出場停止処分を受け、同年は18試合だけの出場で、1972年にはヤクルト・スワローズにトレードされています。
船田和英氏にとっては久々の「お客さんの入る、テレビ中継もある(ジャイアンツ戦だけですが)セリーグ復帰は良かったと思います。1978年のヤクルト球団史上初のリーグ優勝・日本一も経験してますし。
3番のアーロン・ポインターは同年獲得した選手で、22本塁打、67打点とチーム最高の数字を出しますが(打率.260)、当時の感覚の『外人助っ人』としては、ちょっと物足りない数字ですね。
ちなみにこのアーロン・ポインターの妹たちは、アメリカのR&B系コーラスグループ『ポインターシズターズ』でした。
さてもう一人の外人選手のカール・ボレスは、近鉄バファローズで3年活躍後、自由契約になり西鉄ライオンズが獲得した選手で、このカール・ボレスが永易将之に八百長を持ちかけられた事を球団に報告。
更には報知新聞記者にも漏らした事で『黒い霧事件』が発覚しているので、カール・ボレスは高潔なる正義の使徒と、日本プロ野球界に賞賛されてしかるべきですが、この方、ちょいと人間的に問題がある方。
無断で試合欠場したり契約で球団で揉めたり、何かと問題のある選手だったため、チーム内でも評判は悪く、球団にも疎ましがられていたので、カール・ボレスの名前をその後、聞くことはないですね。
翌1971年、シーズン途中でカール・ボレスは解雇されています。
5番の広野功氏は慶應大のスラッガーで、第一回のドラフト会議で中日ドラゴンズに3位指名され、1年目は13本塁打、打点57、打率.277。
新人王は16勝2敗、防御率1,39で、最優秀防御率、最高勝率、沢村賞、更にはノーヒットノーランも記録する驚異の!高卒新人!読売ジャイアンツの堀内恒夫氏でしたが、広野功氏もまずまずの成績でした。
ちなみに1970年、早大からドラフト1位入団で新人王を獲得した、同じく中日ドラゴンズの谷沢健一氏の1年目は11本塁打、45打点、打率.251と、全て広野功氏の1年目より数字は劣っています。
そんな広野功氏でしたが、何故か?3年目に西鉄ライオンズにトレードされ、1970年を最後に今度は読売ジャイアンツにトレードされているので、古のジャイアンツファンならご存知の選手でしょう。
そして、永久追放になってしまったエースの!池永正明氏(現在、復権しています)。
前年までの5年間で99勝をあげていた池永正明氏は、1970年も好調で9試合に登板し4勝をあげましたが、5月に永久追放になってしまいました。
結果的に首位のロッテオリオンズに34ゲーム差をつけられ、西鉄ライオンズは最下位でしたが、結果的にこの投手不足の窮地に、稲尾和久監督に残された戦略は将来有望の若手投手たち起用するしかなかった。
前年8試合登板で0勝2敗、高卒2年目の東尾修投手がこの年は40試合登板。31先発はチーム1で、結果は11勝18敗、防御率5.15と散々でしたが、その後の『200勝投手!東尾修』はこうしてスタートしています。
次に30先発、45登板の三輪悟投手は社会人野球出身とはいえ、1970年はプロ1年目のルーキー!結果はこちらも7勝14敗と散々でしたが、防御率は2.91とまずまずでした。
もう一人!チーム最多登板の51、先発28の、先発三本柱に『そういう事情』でなった河原明投手は、高卒プロ入り3年目ですが、3投手の中では唯一!前年1969年に12勝13敗と実績のあった投手。
18勝の池永正明投手に次ぐチームの勝ち頭だった河原明投手が居たのは、稲尾和久監督もさぞ!救いになったと思います。永久追放になった『永易・益田・与田』3投手合わせても前年は17勝でしたから。
そんな河原明投手は13勝19敗、防御率4,18と、こちらも散々な成績でしたが、この年の西鉄ライオンズは前年に続いてチーム打率はリーグ最下位。打点も盗塁数もリーグ最下位(本塁打はリーグ4位)。
チーム二塁打も三塁打もリーグ最下位の、大きいのは打てても走れない、チャンスに弱い打線では、試合は勝てないですね。